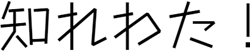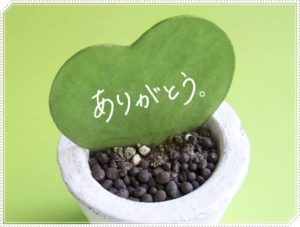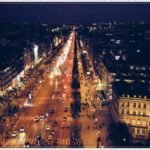毎年9月になるとやってくる、敬老の日。
なんとなく迎える人も多いと思いますが、いざ「どうして始まったのか?」ということを質問されると、なかなか難しいですよね。
そこで今回は、敬老の日が始まった由来や意味などを、簡単に紹介していきたいと思います!
敬老の日が始まったのはいつ?
国民の祝日として、正式に『敬老の日』が制定されたのは1966年(昭和44年)の“国民の祝日に関する法律”の改正から。
建国記念日・体育の日とともに追加され、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」を祝日の趣旨としています。
制定される以前も、9月15日はお年寄りを敬う日として敬老行事が行われていましたが、法律で『敬老の日』という名称に変わったのが1966年だったんですよね。
2003年には、9月の第3月曜日に日付が変更。
そのまま現在に至っています。
敬老の日が9月15日から移動した理由
1980年代から大企業を中心として週休2日が取り入れられはじめ、各省庁、公務員や教育の場でも週休2日制が浸透していきました。
2001年、経済活動の促進や余暇を楽しんでもらうために、特定の祝日を月曜日に移動させて3連休にすることを目的とした祝日改正法(ハッピーマンデー制度)が導入されます。
これに基づき、2003年の法改正で敬老の日も9月15日から9月の第3月曜日へと移動することになったんです。
固定の日ではなくなったので、日にちを覚える必要はありません(´・ω・`)
「敬老の日」の由来とは
敬老の日の由来は、1947年に兵庫県旧多可郡野間谷村で行われた、敬老会と呼ばれるイベントが発端であったと言われています。
当時の村長が、「村の立て直しをするに当たり、経験豊富な老人に知恵を借りたい」と、農業の閑散期である9月中旬に地域の老人を集めて会を催したのです。
その後毎年開催されるようになるのですが、9月15日に敬老会を行うようになった由来について、いくつかの俗説がありますのでご紹介します。
①寺院の建立がキッカケ?
まず1つ目は、悲田院が建てられた日にちなんだ、という説。
悲田院とは、593年聖徳太子によって設立されました四箇院の一つで、老人ホームや孤児院のような施設だったと言われています。
その建設日とされているのが9月15日であると伝えられていたため、敬老のお祝いにふさわしいとして選ばれたという説が出てきているんです。
②元号の改めがキッカケ?
もう一つ目は、717年9月に元正天皇が、野間村の滝を「養老の滝」と命名し、元号を改めたことに由来するという説。
「なんで滝の名前を変えただけで元号が変わるんじゃい!」と感じた人もいるかもしれませんが、まさにそのとおり。
ルーツを辿ってみると、こんな逸話があります。
その泉の水で身体を洗ったところ、お肌はスベスベ・腰痛も治っちゃったというんです。
地元民に話を聞いてみると、あらゆる病気はもちろん、ツルピカになってしまった髪の毛まで生えてくるほどの回復力を持つ「霊泉」であったことが発覚。
「これは……吉兆に違いない!」
そう感じた元正天皇は、元号を"養老"とすることで詔(みことのり)を発したのでした。
こちらもそれっぽい理由ではありますけど、実際の日付がはっきりと記録に残っているとは言い難く、信憑性の高さに疑問が残っているのが現状です。
そもそも滝が出てきていませんし(´・ω・`)
なので、単純に
という説が、一番有力視されています。
スポンサーリンクもとは「老人」「年寄り」の日だった
1950年、それまで一つの村が独自に行なっていた敬老会の日を、兵庫県が祝日として制定したのが『としよりの日』です。
翌年の1951年には、全国の祝日として9月15日は『としよりの日』とされました。
さらに1964年には、国が9月15日を『老人の日』に制定。
その2年後、祝日に関する法律の制定で名称が『敬老の日』に変わり、2003年に日付が移動して9月の第3月曜に制定されています。
なぜこんなに改変が起こっているのかというと、高齢者団体や最初の敬老会を模様した村長が、反対の意向を示したため。
ネーミングも「どストレート」ですからね……仕方なかったのかもしれません。
何歳からお祝いするべき?
では、敬老の日にお祝いされる対象年齢」は何歳以上の方たちなのでしょうか。
そもそも老人・高齢者という呼び方については、明確に何歳から、と指定されているわけではありません。
歴史的・世界的な背景から、これまでは65歳から高齢者とする見解が一般的でしたが、現代の65歳はまだまだ若くて元気な方も多いです。
生涯現役社会と言われているほどですから、「老人扱い」されることに、違和感を持つ方も少なくないでしょう。
医学的にみると、65歳から74歳は前期高齢者、75歳から84歳を後期高齢者、85歳以上の方を超高齢者と区分しています。
個人的には、後期高齢者に当てはまる75歳以上の方はお祝いしてもいいのではと思いますが……これだけだと堅苦しいですよね。
なので、
という認識でいいんじゃないかと思います。
これからも家族を大切に!
いつの時代も変わらず大切なことは、お年寄りを大事にし敬う心ですよね。
いつもは離れている方も、是非おじいちゃん、おばあちゃんに連絡を取ってみてはいかがでしょうか。
プレゼントも良いですが、自分を気にかけてくれている、ということがわかるだけでも嬉しいものだと思いますよ!